診療案内 - 長久手さつき眼科

アピタ長久手 B1
日帰り白内障手術


▲土・日・祝午後:15:00〜17:00
(月・火・木・金が祝日の場合は17:00まで)
※コンタクトレンズが初めての方は受付終了時間30分前までにお越しください。

視力低下、目のかゆみ、痛み、かすみ、ごろごろするなど、目の症状で気になることがありましたらお早めにご来院ください。
目の異常を引き起こす病気には、非常に多くの種類や原因があり同じ病気でも患者様によって症状も変化します。目の病気は自覚症状がないまま進行するものも多く、気づいた時には病気が進行してしまっていることもあります。しかし、目の病気の多くは、早期に発見し治療することによって、症状が改善したり、症状の進行を抑えたりすることが期待できます。
特に自覚症状がない方も40歳を過ぎたら定期的に検査されることをおすすめします。
近視、遠視、乱視、弱視、斜視などの眼症状を対象に、子どもの目の仕組みが完全に発達していない時期(幼児期や学童期)の診療を行います。小児の視力や目の機能は大人とは異なり、成長とともに発達していくため、早期の診断や治療が重要です。
当院は認定視能訓練士が在籍しております。視能訓練士は視力や視機能の発達を促し、治療やリハビリテーションをサポートする役割を担っています。
視能訓練士は、眼科医や看護師と連携しながら、子供の視覚発達をサポートいたします。
白内障とは、年齢とともに目の内側の水晶体が白く濁り、視力が低下する病気です。水晶体は目の中央に位置し、外から目に入ってきた光を屈折させ、網膜に映し出すカメラのレンズのような役目を果たしています。
正常な水晶体は透明なのですが、加齢などによって水晶体の中にあるタンパク質が変性すると、次第に白っぽく濁ってきます。そうすると、水晶体が光を集めても眼底にうまく届かなくなったり、光が乱反射して網膜に鮮明な像が結べなくなったりして、見え方に支障が生じます。
これらの症状に心当たりがある場合は、白内障を発症している可能性が考えられます。
白内障は進行を抑制・予防するための薬物療法と、根治できる手術という治療が可能です。点眼薬や内服薬による薬物療法はかなり初期の白内障には有効ですが、あくまでも進行抑制の効果しか望めません。そのため、生活に支障がある場合には、手術が不可欠です。
当院では患者様のライフスタイルやどの程度生活に支障があるか等、しっかりヒアリングさせていただき、最適な治療法をご提案いたします。
緑内障とは、視神経(視覚をつかさどる神経)が主に眼圧の上昇などによって障害を受け、それが引き金となって視野が障害(視野角が狭くなる)されている状態です。視野障害の進行具合は非常に緩やかなため、自覚症状が乏しく、病状がある程度進んで視野が狭まることによって気づくケースが多いです。視野障害を一度受けてしまうと、その部分は回復しません。そのため、放置したままにすると失明する可能性があります。緑内障は日本人が中途失明する原因の第1位です。
緑内障は40歳以上の方の20人に1人の割合で発症すると言われています。早期発見・早期治療を可能にするには、40歳を過ぎたらこれといった眼症状がなくとも眼科検診を受けるようおすすめしています。
視野の一部に異常が見られますが、範囲が小さかったり、視野の端の方だったりするために、気づかないことも多くあります。
視野の中で見づらい部分も出てきますが、発症していない方の目でカバーしてしまうため、気づかない人もいます。老眼と重なる場合も多く、発見に至らない場合もまだ多い状況です。
視神経の40〜50%に障害が及ぶと、視野の中心部分も見えなくなり、内側(鼻側)から視野が狭くなっていきます。テレビを見ていても見えないところが出てくるなど、日常生活にも支障が出てきます。
緑内障と診断されたら、まず眼圧を下げるための点眼薬による薬物療法となります。
点眼だけでは眼圧が下降しない、症状の進行が抑えられないという場合は、レーザー治療として線維柱体にレーザーを照射して房水を排出させやすくするレーザー線維柱帯形成術や、主に閉塞隅角緑内障に対して行われるレーザー虹彩切開術(虹彩の部分にレーザーを照射してバイパスを作成し、房水を排出させやすくする )などがあります。
また、薬物療法やレーザー治療でも眼圧のコントロールが不十分な場合、手術療法を行います。
結膜炎は、目の表面を覆う結膜に炎症が生じる疾患です。主な原因は、ウイルスが原因で発症する流行性角結膜炎(アデノウイルス感染)や細菌性のもの、アレルギー性のものがあります。
ものもらいは、まぶたの縁にできる腫れやしこりのことを指します。主に「麦粒腫」と「霰粒腫」の2種類があります。
細菌感染によってまぶたの縁やまつ毛の根元にある脂腺が化膿する疾患です。
赤み、腫れ、痛み、膿がたまることがあります。
抗生物質の点眼薬や軟膏で治療します。膿がたまっている場合は、医師が切開して排膿することもあります。
細菌感染が原因ではなく、まぶたの脂腺が詰まり、しこりができる状態です。
しこりができるが、痛みが少ないか、全くないことが多いです。
自然治癒することもありますが、改善しない場合は外科的に切開することもあります。
涙は、目の栄養補給と保湿の役割を担っていて、目の外上側にある涙腺から分泌されます。分泌された涙は、上下の眼瞼縁に溜まって眼球を潤しつつ、古い涙は目頭にある涙点から瞬きをするごとに涙管を通り鼻腔へと排出されていきます。涙点から鼻腔までの涙の通り道のことを涙道と呼びます。この涙道のどこかが詰まってしまうと、涙がうまく排出されずに溢れ出てくるようになります。流涙症では、涙を拭き続けなければならない、涙でものが見えにくい、眼の周りがかぶれてしまうといった症状を伴うこともあります。
原因としては、「分泌性流涙」と「導涙性流涙」の大きく2つに分けることができます。
分泌性流涙は、外から刺激によって起こる流涙症です。逆さまつげや結膜炎や角膜炎、ドライアイなどが原因となって過剰に涙が分泌される状態です。
導涙性流涙は、涙道閉塞が原因によって起こる流涙症です。鼻涙管閉塞症などが代表的ですが、副鼻腔炎(蓄膿症)など鼻の病気が原因となって起こることもあります。
逆さまつげ等による刺激が原因の場合は、原因となっている逆さまつげ等を取り除くことで治療します。
まぶたやまぶたの位置に異常がある場合は、手術が必要です。 涙の通り道が詰まっている場合には、詰まっている部分を広げたり、迂回する道を作る手術が必要になります。
流涙症は他にもさまざまな原因があり、原因に応じた治療が必要になります。 気になる症状がありましたら、まずは眼科で検査を受けましょう。当院でも治療可能ですので、お気軽にご相談ください。
体内に入った異物に対して体が過敏な反応を起こすことをアレルギーといい、結膜でこの反応が起きる病気をアレルギー性結膜炎と呼びます。目(結膜)は直接空気に触れるためさまざまな異物が入りやすく、それらがアレルギー反応を起こす原因物質(アレルゲン)となります。原因物質の代表的なものとしては花粉、ハウスダストなどが挙げられ、それらが結膜に触れるとかゆみ、充血、目やになどの症状を引き起こします。また激しいかゆみや角膜に白い混濁を生じる春季カタルや、コンタクトレンズの汚れが原因で発症する巨大乳頭結膜炎も、アレルギー性結膜炎の一種です。治療法や予防法は原因物質によって異なるため、まずは原因を特定して適した治療を行っていきます。
花粉症の場合はこのような目の症状に伴い、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が出ることもあります。強い症状が長く続くと集中力の低下や頭痛、倦怠感を引き起こすこともあります。
点眼薬による薬物療法が基本となります。
症例や症状の程度に応じて飲み薬や点鼻薬を使用して症状を抑えます。
花粉が原因物質である場合は、花粉が飛び始める2週間程度前から薬による治療を始める「初期療法」によって、症状が出るのを遅らせたり、症状を軽くすることが期待できますので、早めにご相談ください。
パソコンのモニター画面やスマートフォンを長時間眺めるなど、近距離にピントを合わせる機会が増えてきました。このように、目の筋肉の使いすぎや瞬きの回数が減少することで眼精疲労を引き起こします。目の痛みや充血、ぼやける・視界のかすみ・眩しさを感じるなどの症状のほか、頭痛・肩や首の凝り・めまい・吐き気などの全身症状も現れます。十分に休ませても回復しない状態を眼精疲労と言います。ドライアイは日本では5人に1人が罹患していると言われるほど増えている疾患です。目は涙によって乾燥から守られていますが、ドライアイは涙の量の不足や涙の質のバランスが崩れてしまい、目の表面を乾燥から守ることができなくなってしまっている状態です。エアコンの風やパソコン・スマートフォン、コンタクトレンズもドライアイの大きなリスク要因であり、近年は子どもを含めた幅広い層の発症が増えているといわれています。ドライアイのさまざまな症状は眼精疲労の原因となりやすいといわれています。
また、目だけではなく、肩・首がこる、頭痛がする、倦怠感があるなど全身症状も現れる場合があります。
眼精疲労に対する特効薬は残念ながらありません。
原因に対する治療に加えて、ビタミン剤の配合された点眼薬や内服薬、サプリメントなどが有効な場合もあります。
また、環境や仕事スタイルの見直しも大切です。パソコンの画面との距離や姿勢はどうかなど、少し意識するだけで、症状の緩和に繋がる可能性があります。
ドライアイの治療方針は、涙の水分の蒸発を抑えること、涙の水分量を増やすこと、目の表面の炎症を抑えることで、点眼が第一選択です。
点眼以外の治療には、副交感神経刺激薬の内服や涙点に栓(涙点プラグ)をして涙を貯める手術があり、これらは涙の水分量を増やす効果があります。
患者様の生活スタイルにあわせた適切な眼鏡、コンタクトレンズの処方を行います。
ご自身の視力にあっていないものを使用し続けると頭痛や眼精疲労などの原因になる場合もあります。
また、コンタクトレンズは眼に直接装用する高度医療管理機器であり、適切な使用をしないと感染症などをきたし、重篤な視力障害をきたす可能性があります。
当院では患者様に安心してコンタクトレンズを装用した生活を楽しんでいただけるよう、装用練習、管理ケア方法をスタッフが丁寧に指導いたします。
特に目の状態に不具合がない場合も、視力も変化しますので定期的に検査を受けましょう。
装用練習にお時間がかかります。お時間に余裕をもってご来院ください。
また、ご使用中の眼鏡をお持ちの方は、ご持参ください。
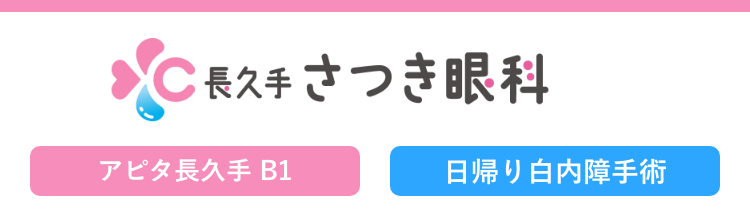
| 予約 | アクセス |